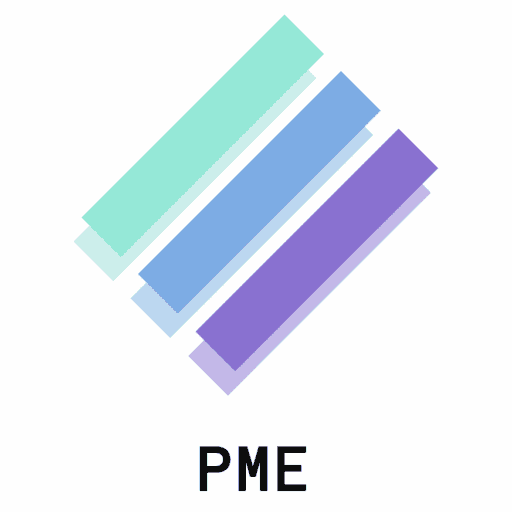「何を聞かれるの?」「どう答えればいいの?」という不安に答えます
筆記試験に合格し、いよいよ最終ステージである口頭試験へ。
しかし多くの初受験者が感じるのが、
「どんな質問が出るの?」「どう答えたら評価されるの?」という不安ではないでしょうか。
結論から言えば、口頭試験では“難しい知識”よりも“整理された説明力”が求められます。
つまり、「何を」「どう伝えるか」で合否が大きく分かれます。
この記事では、
- 実際によく聞かれる質問の傾向
- 面接官が見ているポイント
- 合格者が実践している答え方の型(PREP法)
をわかりやすく紹介します。
口頭試験の質問は「あなたの経験」を掘り下げるもの
技術士の口頭試験では、専門知識を深掘りする質問よりも、
あなたの実務経験・判断力・説明力を確認する質問が中心です。
PMEの模擬面接データから見ても、質問の約7割は次の3つに分類されます。
| 質問の種類 | 内容の例 | 面接官が見たいポイント |
|---|---|---|
| ① 自己紹介・業務説明 | 「あなたの担当業務を3分で説明してください」 | 経験を整理して話せるか |
| ② 筆記試験関連 | 「筆記試験で書いたテーマについて説明してください」 | 筆記内容を理解しているか |
| ③ 行動・判断を問う質問 | 「トラブルが起きたとき、どのように対応しましたか?」 | 責任感・判断力・倫理観 |
つまり、“正しい答え”よりも“自分の考えをわかりやすく伝える力”が問われるのです。
面接官が見ているのは「整理力」と「再現性」
面接官は、あなたの知識量を測るのではなく、
「この人が技術士として自立した判断を下せるか」
「わかりやすく説明できる力があるか」
を見ています。
そのため、話が長い・論点がぼやけている・順序が前後している、
といった説明は減点対象になりやすいです。
一方で、話の構成が明確で、結論が最初に示されている受験者は、
内容が多少浅くても「理解している」「説明力がある」と評価されます。
ここで有効なのが、シンプルで応用の効くPREP法です。
PREP法とは? ― 技術士口頭試験で最も効果的な答え方の型
PREP法は、ビジネスやプレゼンでもよく使われる「説明の基本構成法」です。
4つのステップで、短時間でも論理的な説明ができます。
| ステップ | 内容 | 例:『リスク対策をどう進めましたか?』に答える場合 |
|---|---|---|
| P(Point) | 結論を先に述べる | 「私は事前リスク評価の仕組み化を行いました。」 |
| R(Reason) | 理由を説明する | 「トラブルの再発防止には、属人的な判断を減らす必要があったからです。」 |
| E(Example) | 具体例を出す | 「工程ごとにチェックリストを作成し、月次レビューを実施しました。」 |
| P(Point) | 結論を再確認する | 「この結果、作業のばらつきが減り、品質トラブルがなくなりました。」 |
この構成を意識するだけで、話が整理され、短時間で伝わる説明になります。
PREP法を使うとこんなに変わる!
同じ内容でも、PREP法を意識するだけで印象が大きく変わります。
❌ 悪い例(だらだら型)
「現場でトラブルがありまして、原因を調べたら…(中略)…いろいろ大変でしたが、何とか対応できました。」
👉 結局何をしたのかが分かりにくい。
話の順序もバラバラで、聞き手が整理しづらい。
✅ 良い例(PREP法)
「私は再発防止のために手順書を標準化しました。(P)」
「原因の一つは担当者による判断のばらつきでした。(R)」
「そこで工程ごとに確認項目を明確化し、教育も行いました。(E)」
「結果として、同様のトラブルは半年間発生していません。(P)」
👉 内容は同じでも、結論が明確で、印象に残る説明になります。
PREP法を身につける練習方法
PREP法は「知っている」だけでは意味がありません。
実際に声に出して練習することで、口頭試験本番でも自然に使えるようになります。
練習ステップ
- 想定質問を5つピックアップする
- PREP法に沿って簡単なメモを作る(キーワードだけでOK)
- 録音しながら2分以内で答える練習をする
- 自分の録音を聞いて、
- 結論が先に言えているか
- 「理由」「具体例」が明確か
- 冗長になっていないか
をチェックする
📌 PMEの模擬面接では、このPREP法をベースにしたフィードバックを行っています。
「内容は良いのに伝わりにくい」を防ぐ実践的な練習が可能です。
👉 PMEの口頭試験向け模擬面接(オンライン)サービスを見る
よくある質問と注意点
Q. PREP法で話すと、形式的に聞こえませんか?
→ 問題ありません。
大切なのは「流れ」ではなく「伝わりやすさ」です。
形式にこだわるより、「相手が理解できるか」を意識しましょう。
Q. 面接官の質問が途中で変わったらどうすればいい?
→ 途中で質問意図がずれても、P(結論)から入るのが正解です。
そのあとで理由や事例を補足すれば、焦らず対応できます。
まとめ|“伝える力”こそ合格への最短ルート
- 口頭試験の質問は「知識」より「説明力」を見ている
- PREP法で「結論→理由→具体例→まとめ」の流れを意識する
- 録音練習や模擬面接で実戦的に身につける
技術士に求められるのは、技術だけでなく「人に伝える力」です。
PREP法をマスターすれば、どんな質問にも落ち着いて答えられるようになります。
あなたの経験を、あなたの言葉で。
その一歩を、今日から始めましょう。