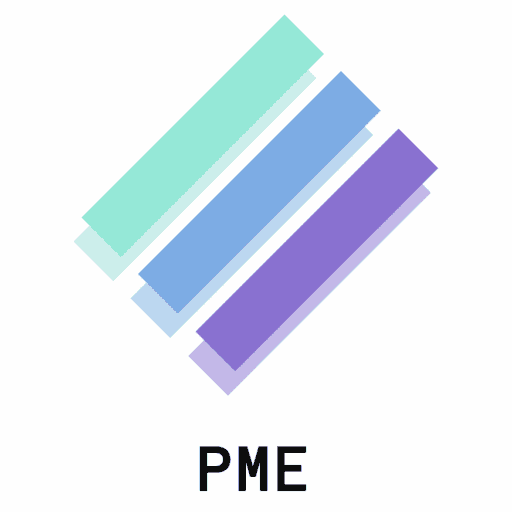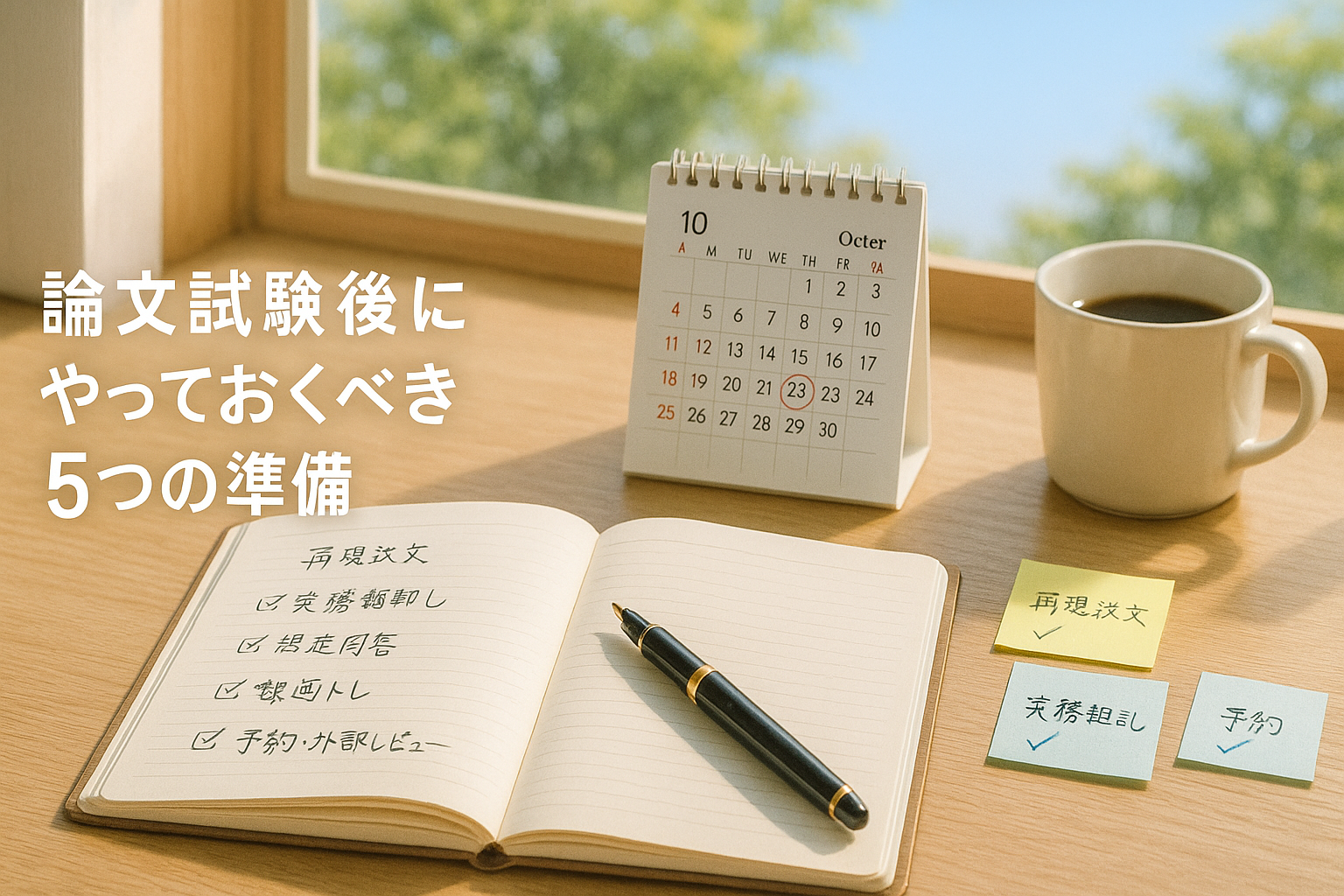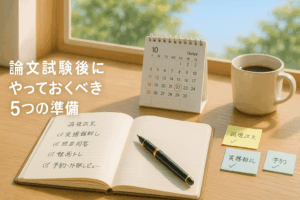技術士二次の論文試験を終え、合格発表(10月末)まで約2か月。期間に余裕はあるけれど、合格の確信まではない――そんな時期こそ、疲れを抜きつつ“落とさない準備”が効きます。発表後すぐに口頭モードへ移行できるよう、いまやっておくべき5つの準備を厳選してまとめました。
目次
1) 本番同等の「再現論文」を仕上げる(2〜3時間×1回)
- 試験当日のメモ(キーワード/骨子/図表の構成)を頼りに本番と同じ段落構成で通し書き。
- 曖昧な箇所は〔要確認〕と残し、後日、業務資料で裏取り。
- 目的は口頭で問われたときの整合性確保(「なぜその対策?」「数値の根拠は?」に即答できる土台)。
チェックリスト
- 出題主旨の解釈が明確
- 課題→原因→対策→効果/留意点の因果が通っている
- 具体数値・規格・事例の根拠が示せる
- 自分の責任範囲・判断プロセスが書けている
2) 会社の業務を振り返る「実務棚卸しノート」を作る(30〜60分/回×2回)
直近2〜3案件をCAR/STARで短文化しておくと、そのまま口頭の骨子になります。
テンプレ(STAR)
- S(状況):プロジェクトの背景(顧客/仕様/制約)
- T(課題):技術的/組織的な課題(安全・品質・納期・コスト)
- A(行動):あなたが取った具体的行動(代替案の比較、規格準拠、解析/実験)
- R(結果):効果(KPI/数字)と副作用・学び
追記する数値・事実
- 主要KPI(例:歩留まり、CT、稼働率、PPM、不良率、納期)
- 関係者・意思決定の経緯(合議/権限/判断根拠)
- リスク評価と代替案の選定理由
3) 想定問答リストを作る(まず10問)
汎用10問(例)
- 最近の主担当プロジェクトを60秒で説明
- その課題と解決策
- 安全・品質・倫理で留意したこと
- リスク評価と代替案
- 成果の定量指標
- 技術的根拠(規格・データ)
- 自分の役割と意思決定
- 失敗からの学び
- 継続研鑽の計画(学習・資格・学会)
- 受験動機と技術士としての抱負
各問は結論→根拠→効果/限界の順で150〜200字に圧縮。
4) “口慣らし”の録画トレ(20分×週2回)
- スマホで60秒要約→120秒詳細→60秒リスクのリズム練習。
- チェック観点:結論先出し/数値と規格の具体性/倫理・安全への言及/代替案の有無。
- 録画を見返し、話の構造(見出し語)と口癖/冗長表現をメモして修正。
5) 導線を整える(予約・外部レビュー・環境)
- 予約の先取り:合格発表直後は模擬面接の需要が急増。希望日だけでも仮押さえを。
- セカンドオピニオン活用:再現論文は第三者レビューで「設問適合」「論理の連結」「弱点論点」を短時間で点検。
- 生活リズム:就寝/起床を±30分で固定。週1は完全オフで回復優先。
2か月の“ゆる計画”(例)
- Week1:再現論文を完成(2〜3h、2日に分割OK)+実務棚卸し①
- Week2:想定問答10問作成+録画トレ×2
- Week3–6:録画トレ×週2+棚卸し②で数字の裏取り
- Week7:外部レビューで設問適合性チェック(単発添削)
- Week8:合格発表直後に模擬面接で最終調整(録画&弱点フィードバック活用)